 「アイン」と
「アイン」と 「ハムザ」)、「ハ行」に聞こえる音が3つ(
「ハムザ」)、「ハ行」に聞こえる音が3つ( /
/ /
/ )、"s" と "t" の強勢音が存在するなど、日本語にはない音がたくさんあるので、カナ書きで覚えるのも厳しいと言える。その反面、母音は易しく、口語でも「あいうえお」で対応可能。
)、"s" と "t" の強勢音が存在するなど、日本語にはない音がたくさんあるので、カナ書きで覚えるのも厳しいと言える。その反面、母音は易しく、口語でも「あいうえお」で対応可能。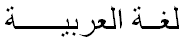 アフロ・アジア(セム・ハム)語族/ アラビア文字表記
アフロ・アジア(セム・ハム)語族/ アラビア文字表記




イラク、クウェート、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦、オマーン、サウジアラビア、イエメン、ヨルダン、イスラエル、パレスチナ、シリア、レバノン、エジプト、リビア、スーダン、ソマリア、ジブチ、チュニジア、アルジェリア、モロッコ、西サハラ、モーリタニア、コモロ連邦、マルタ
主に西アジアから北アフリカにかけての広大なイスラム教圏で話されており、話し手人口は2億から3億人ほどと推定されている。国連の公用言語のひとつ。伝播からの長い年月と、広大な領域のために方言化が著しく、最東端のイラクと最西端のモロッコでは意思の疎通が困難なほどである。
全体的に摩擦音が多く、声門閉鎖音、咽頭音などさまざまな子音のバリエーションをもつ。反面、単母音は正則アラビア語では3つしかない。
アラビア文字で表記されるので、通常は母音を表記しない。通常表記から正確に発音するのは慣れない限り難しい。文字そのものは書きやすく、28文字しかないので覚えやすいと言える。
他の言語から応用できる発音が少なく、全体的に難しい。声門閉鎖音が2つ( 「アイン」と
「アイン」と 「ハムザ」)、「ハ行」に聞こえる音が3つ(
「ハムザ」)、「ハ行」に聞こえる音が3つ( /
/ /
/ )、"s" と "t" の強勢音が存在するなど、日本語にはない音がたくさんあるので、カナ書きで覚えるのも厳しいと言える。その反面、母音は易しく、口語でも「あいうえお」で対応可能。
)、"s" と "t" の強勢音が存在するなど、日本語にはない音がたくさんあるので、カナ書きで覚えるのも厳しいと言える。その反面、母音は易しく、口語でも「あいうえお」で対応可能。
| 格表示 | 屈折を持つが、多くの場合、語順 |
| 語順 | 名詞文: 主語 − 補語 動詞文: 動詞 − 主語 − 目的語となる。 |
| 冠詞 | 定冠詞がある。性や格による変化はない。 |
| 限定詞 | 指示詞は前置。あとは後置が基本。性・数に合わせて変化するが、「物」の複数形には女性単数形を用いる、という規則がある(動詞などにも適用される)。 |
| 名詞 | 男性、女性の2性。格は主格、属格、対格の3段階でそれぞれ定形-不定形の形を持つが、口語では発音されないうえ、変化は非常に易しい。例外的な変化も難しくない。単数形 - 双数形は語尾で区別する『規則変化』だが、複数形は多くの場合、母音変化や接辞によって表す『不規則変化』で、こちらは難しい。 |
| 動詞活用 | 話法に直説法、命令法、接続法、要求法の四つがある。人称・数にあわせそれぞれ13の形を持つ。 三子音(二子音または四子音もある)から成る単純な形の『基本動詞』と、それに接頭辞、接尾辞、接中辞を加えた形の『派生動詞』がある。他動詞/自動詞の区別は主に派生動詞を用いて行う。 |
| おさえておきたいところ | |
| まず三子音語根構造を理解する。男性/女性名詞の区別はヨーロッパ系言語に比べれば簡単。しかしながら、名詞・形容詞の単数 - 複数の変化、動詞の活用、基本動詞と派生動詞の用法など、覚えることが多いので、学習するのに非常にやりがいのある言語と言える。 | |
単語の派生力が強いので、外国語からの借入の割合は比較的少ないと思われる。西欧語の他にはペルシャ語やトルコ語からの語がいくらかある。
アラビア語起源の単語は英語を通して日本語にも意外にたくさん入っている。マガジン、ハザード、ソファー、シャーベット、ジャスミンなど。アラビア語に日本語がどれくらい入っているのかは知らない。国によって差がありそう。
縁戚関係で習得に応用できる言語としては、公用語クラスはヘブライ語とマルタ語くらいしかない。エチオピアのアムハラ語や北アフリカのトゥアレグ語などは遠い縁戚語なので応用は難しいかもしれない。
しかしながら、イスラム教の聖典コーランはアラビア語で書かれているため、イスラム教圏ではアラビア語の語彙が借入されている例が多い。なのでアラビア語の語彙の知識をペルシャ語(『方言』の関係にあるダリー語、タジク語も)、ウルドゥー語/ヒンディー語の修得に応用することは可能だったりする(意味や形が変わっているものもけっこうあるけど)。その他、トルコ語を始めとするテュルク諸語やマレー語にもアラビア語系の単語はたくさんあるので、知識の応用は可能である。
英語
ポルトガル語
スペイン語
フランス語
ドイツ語
ロシア語
ヒンディー語/ウルドゥー語
ベンガル語
マレー/インドネシア語
中国語(普通話)
日本語